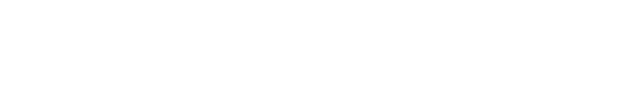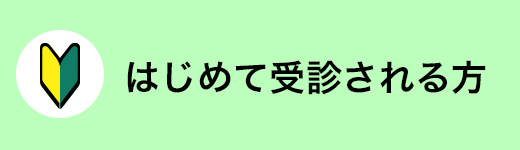グループプロフィールBook
皆様、こんにちは!
エデュケアライズグループのCSO(最高戦略責任者)の山村です。
今回は、今年度初めての試みである、『グループ視察』について共有させていただきます。エデュケアライズグループは、現在スタッフが240名を超え、4つの法人格の中で28の事業が栃木県内を中心に動いています。
さて今回は、グループの取り組みの1つでもある『プロフィールBook』をご紹介します!その名の通り、職員を知ってもらうための冊子です。職員一人ひとりを理解するために以下の内容が入っています。
-
所属法人
-
所属施設
-
名前
-
役職、資格
-
入社年度
-
出身地
-
血液型
-
部活経験
-
好きな言葉
-
得意なこと
-
今ハマっていること
-
自分の沸点
-
一生に一度は行ってみたいところ
-
スタッフへメッセージ
都度グループのイベントや交流会などが活発ということもあり、人柄や性格などが入口の部分でもコミュニケーションのキッカケとしてとても役立っているという声は有難いですが、お聞きします。
是非参考にしてみてください!
さて話は少し変わりますが、実は今までは、社員のほとんどを新卒で採用してきた、グループ会社としては珍しい会社かもしれません。
一方で、短大の廃校や入学率の低下にも伴い、キャリア採用も積極的に進めており、この3年くらいは特に力を入れています。以前は新卒中心のカルチャーが強すぎて、キャリア採用でせっかく入社してもらってもうまくなじめずに退職するということも少なくありませんでしたが、色々と改善を進めており、定着率も上がってます 。
キャリア採用で入社した社員に我々のEducarealize Groupの印象を聞くと、「とてもいい人が多い」「雰囲気が良い」という答えがよく返ってきます。
ではせっかくですので、どういうところが“いい人”なのかと聞くと、足を引っ張らない、陰口を言わない、派閥がない、質問したら快く答えてくれるなどが挙がります。「こういうことは当たり前のことではないですよ。」と言ってくれるスタッフも多く、私としてもありがたいことです。
手前味噌ではありますが、どうしてEducarealize Groupには「いい人」が多いのだろうということを考えてみましたグループの採用が人間性を過度に重視しているということはありませんし、他社に比べて人間性が優れた人が応募してくるということでもありません。
世の中のほとんどの人は「いい人」なのだろうと思うのですが、組織というのは「いい人」を続けられなくさせる理念やコンセプトが働くものです。グループとしてそれを自覚していて、「いい人であり続けられる職場・文化や雰囲気」を連綿と磨き続けてきたということが言えると思います。それらの取り組みを少しご紹介します。
前回の内容にも触れるかもしれませんが、まずグループでは、誰かのために働くからこそ人生に価値があるを人材育成の柱として、人間力の向上に取り組んでいます。これは一過性の掛け声とか、表題ではなく、トップからのメッセージや仕事中のやり取りなどを通じて日頃から相当徹底しており、意識と行動を高めています。
また、親御さんをご招待しての歓迎会など、身近な人から幸せにしていこうという価値観が実感できるような行事も継続しています。利他と自責の実践を通じた人間力の向上に取り組んでいることが、ベースとして“いい人”作りにつながっているのかもしれません。
次に、全社の連帯感を高め、派閥を作らない、風通しの良い雰囲気づくりです。組織の風通しが悪いと、現場の問題と言われますが、一番の問題は上層部です。上層部の風通しが良くて、現場の風通しが悪いという組織はほとんど見たことがありません。(現場は連携がよいのに上層部は悪いというケースはよくありますね)風通しの良い組織づくりは、まず上層部からです。
最後に、誰もが勝者になれる制度づくりです。まだまだ改善の余地はありますが、私はグループメンバー全員が主役であり、地域社会に新しい価値を見出すクルーでもあると思っております。
Educarealize Groupでは組織力というものが企業競争力の重要要因だと考えています。そして最終的にそれが差別化になり、必要とされる存在になり得ると思います。そのため、派閥化や足の引っ張り合いなどが起こるような仕組みや風土はできる限り排除することは当然ですし、努めています。一方で、風通しの良さや協力関係の向上のために必要なことは何かを常に模索して、実行しているつもりです。
ほぼすべての社員は“いい人”でしょうし、モチベーションだってあります。ところが、モチベーションを下げる言動が飛び交い、“いい人”でいられなくなるような仕組みや風土がある会社が少なくありません。
まずはそうした言動や仕組みをなくしていくこと、そのうえで誰もが活躍できる組織づくりをしていくこと。これが大事な順序だと考えて取り組んでいます。